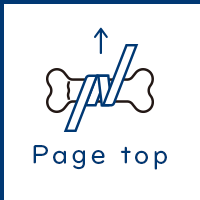- 突然、体の片側だけ(顔、手、足)にしびれや麻痺が起こった
- しびれと共に、激しい頭痛、吐き気、めまいがある
- ろれつが回らない、言葉が出にくい、物が二重に見える
- 急に尿や便のコントロールができなくなった
- 両手足のしびれや麻痺が急激に悪化(進行)した
これらの症状は、脳や脊髄など中枢神経の異常を生じている可能性があります。できるだけ早く救急外来や脳神経外科を受診するようにしてください。

腕や手・足が痛い、しびれる

腕や手、足に感じる「痛み」や「しびれ」は、日常生活の支障になります。一時的(一過性)のものから、重篤な病気が原因となっているものまで様々です。
これらの症状は、脳や脊髄など中枢神経の異常を生じている可能性があります。できるだけ早く救急外来や脳神経外科を受診するようにしてください。
整形外科の受診を検討した方がよい症状は以下に挙げるものです。
これらの症状は、身体のどこかで神経や血流が悪いことを示している可能性を考えます。
症状が続く場合には整形外科専門医の受診をお勧め致します。
腕や手、足の痛み・しびれの根本的な原因として、以下の3つのパターンが考えられます。
脳や脊髄から枝分かれした神経は全身に張り巡らされていきます。その神経の通り道である「首(頚椎)」「腰(腰椎)」「手首」などで圧迫されると、その先の手足にしびれや痛みとして現れます。
身体の代謝や血液の循環に関わる病気が原因で痛み・しびれを生じることがあります。
これらは非常に緊急性の高い病気です。
医師による診察や検査により痛みの原因を診断し、その後それぞれの生活様式や習慣に即した治療方法をご提案致します。治療は、原因となっている神経の炎症を抑えたり、血流を改善したりすることを目的とした保存療法(手術をしない方法)で症状の軽減を図っていきます。
痛みや炎症を抑える薬や、神経の痛みを鎮める薬、血行を促進する薬などを使用します。
理学療法士がマンツーマンで行う運動療法を中心に治療を行います。姿勢の改善指導やストレッチによって、硬くなった筋肉や関節の動きを改善することで、神経への圧迫を軽減します。温熱療法や電気療法といった物理療法も組み合わせることで治療効果を上昇させます。
サポーターやコルセットなどで患部を安静に保ち、神経の圧迫を防ぎます。
ご自宅でも症状緩和に努めることが大切です。以下をご参考にしてください。
特にしびれは血行不良で悪化しやすいため、お風呂で温めるなどして血行を良くすることを心がけましょう。
長時間のスマホ操作やデスクワークで首を前に突き出す姿勢は特に注意が必要です。座る際は深く腰掛け、背筋を伸ばし、画面の高さを目の高さに合わせるようにしましょう。
ウォーキングなどの適度な運動も有効です。また、疲労やストレスは症状を悪化させる可能性があるため、十分な睡眠と休息をとりましょう。
腕や手・足の痛みやしびれは、対象が整形外科だけでないことがある症状です。受診を急ぐべき症状には特にお気をつけください。気になる点がございましたら当院でもご相談ください。
腕や手、足の痛みやしびれは、神経や血流、関節、筋肉の異常が原因で起こることがあります。症状の出る部位やしびれの程度によって、頸椎や腰椎の神経圧迫、血行不良、炎症性疾患など、さまざまな可能性が考えられます。早めに原因を特定し、適切な対処をすることが大切です。
肘関節を形成している骨(上腕骨、尺骨、橈骨)の先端は、関節軟骨に覆われており、骨にかかる衝撃を緩和しています。
肉体労働での肘関節の使いすぎによる発症や、野球やテニスなどで肘関節を痛め、のちに50~60歳代になって発症するケースもあります。骨折の治療後に変形することもあります。
上腕骨外側上顆炎は、「テニス肘」や「ゴルフ肘」とも呼ばれています。肘から前腕には、手首を動かしたり、指を曲げたりする筋肉が重なるように存在し、その中の一つに短橈側手根伸筋(たんとうそくしゅこんしんきん)という筋肉があります。テニスなどで同じ動作を何度も繰り返し、過度な負担がかかることにより、この筋肉に亀裂や炎症が生じて痛みが起こると考えられています。また、日常生活の中で毎日包丁を握る、ゴルフでクラブを握るといった握る動作の繰り返しや、パソコンやスマホの操作のしすぎで発症することもあります。
野球肘とは、投球動作の繰り返しによって起こる肘の障害で、肘関節を保護している軟骨や靭帯、筋肉、腱などが損傷する病態の総称です。医学的名称は上腕骨内側上顆炎(じょうわんこつないそくじょうかえん)といいます。肘への負荷が過剰になることが原因です。
腱鞘炎(けんしょうえん)は、手の使いすぎによって指や手首の関節などに痛みが生じる疾患です。手首の母指(親指)側にある腱鞘(けんしょう)と、その部分を通過する腱の間で摩擦が起こり、手首の母指側が痛んだり、腫れたりします。安静にして手を使わなければ腫れは引きますが、使い続けると腫れや痛みが強くなります。スポーツや仕事で指を多く使う方によくみられます。
スポーツの活動中などに、一度の大きな外傷で発生します。ラグビーや柔道で、選手同士の接触により膝を強くひねったり、バレーボールやバスケットでのジャンプ着地時に強い衝撃を受けたり、サッカーやバスケットでの急な方向転換などが原因で起こります。スキーの転倒などでも多い膝の外傷です。
靭帯を損傷すると、動けなくなるほど激しい痛みが生じ、断裂するとそこからの出血が関節内にたまり、腫れが目立つようになります。膝の屈伸も困難になってきます。
後十字靭帯損傷は、膝から下の部分が後方に押し込まれるような強い力がかかったときに発生します。膝を直角に曲げた状態で、地面に強く膝の前面を打ち付けたり、ラグビーのようなコンタクトスポーツで、正面から膝下にタックルを受けたり、交通事故で車が急停車してダッシュボードに膝(脛骨の上端部)がぶつかり強い衝撃を受けたりすることで起こります。
損傷すると激しい痛みが起こり、膝の曲げ伸ばしがうまくできないといった可動域制限とともに、膝全体に腫れが生じます。膝裏を押さえると痛みを認めます。また、放置した場合や損傷の仕方によっては、膝関節に不安定性を残すことがあります。
半月板は、大腿骨(だいたいこつ:太ももの骨)と脛骨(けいこつ:すねの骨)の間に存在する軟骨性の板で、左右の膝関節に2枚ずつあります。アルファベットの「C」に似た形状で膝の内側と外側にあり、膝のクッションとして機能し、周辺の関節軟骨を保護する役割を担うほか、膝の安定化や脚の屈伸もサポートしています。この半月板が傷ついてしまった状態を半月板損傷といいます。
初期は、運動後に膝の不快感や鈍痛がある程度でほかに特異的な症状はなく、痛みがあっても運動はできます。しかし進行して軟骨の表面に亀裂や変性が生じてくると痛みが強く現れ、スポーツなどに支障がでてきます。軟骨が剥がれて軟骨片が関節の中に遊離すると、膝の曲げ伸ばしの際に引っかかり感やズレ感が生じます。大きな軟骨片が遊離すると膝の中でゴリッと音がしたり、関節に挟まると膝がロックして動かなくなったりすることもあります。
初期や軽度の場合、運動療法や薬物療法(鎮痛剤やヒアルロン酸注射)で痛みを軽減し、日常生活を送ることが可能です。膝を温めるホットパックや低周波などの消炎鎮痛療法、膝を安定させるためのサポーターや足底板(足の下の中敷)などの装具療法が有効なこともあります。重度の場合は手術治療を検討します。
膝蓋腱炎は、オーバーユース(使いすぎ)に起因する膝のスポーツ障害で、ジャンプ動作を繰り返す競技でよく見られることから、ジャンパー膝とも呼ばれています。バレーボールやバスケットボールなどでジャンプや着地動作を頻繁に繰り返したり、サッカーの蹴る動作やダッシュなど、膝の曲げ伸ばしを頻繁に繰り返したりするスポーツで多くみられます。走ることが多い陸上競技でも起こります。日常的にスポーツを行う10代~30代の若い世代に好発する疾患です。また、スポーツでなくても体が硬い人などで、体力増進のためにランニングや急に走ったり、歩いたりすることで発症することもあります。
典型的な足関節の捻挫は、足首を内側にひねることによって生じる足関節内反捻挫です。足関節の外側(外くるぶしの付近)にある前距腓靱帯(ぜんきょひじんたい)が、引き伸ばされたり、一部が切れたりすることで起こります。靭帯の損傷の程度には1度から3度までの分類があります。
アキレス腱は、足首の後面にある人体の中で最も太い腱で、ふくらはぎの筋肉とかかとの骨をつないでいます。アキレス腱断裂とは、その一部(部分断裂)またはすべて(完全断裂)が切れた状態のことです。30~40歳代が受傷の好発年齢ですが、10代から高齢者まで幅広い年齢で起こる可能性があります。テニス、野球、サッカー、バレーボールなどのスポーツ活動中に、踏み込み、ダッシュ、ジャンプ、ターンといった動作で、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋:かたいさんとうきん)が急激に収縮して、アキレス腱に強力な牽引力がかかったり、着地動作などで急に筋肉が伸びたりしたときに断裂が起こります。階段を踏み外したときなど、スポーツ以外の日常動作でも起こることもあります。
痛風は、「患部に風が当たるだけで痛みが生じる」ことからこの病名が付けられたといわれています。足の親指の付け根に、ある日突然、腫れと激痛が走ることから始まり、数日は歩けないほどですが、1週間~2週間程度で痛みは治まってしまいます。ただし治療せずに放置していると、痛みの発作を繰り返して症状が悪化するだけでなく、結石などの合併症が生じることもあります。発作のほとんどは足の親指の付け根に起きますが、足首や膝、手、肩など、どこの関節にも起こる可能性があります。30~50代の男性に多くみられる疾患です。